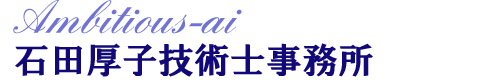9月になったが猛暑は終わらない。ただ、吹く風はなぜか涼しくなったような気がする。過ぎて行った8月は、80年前に2つの原爆が投下され、第2次世界大戦に敗戦した、日本にとって忘れがたい月である。毎年、戦争体験者の声を聴き、それを後世に伝えるべきだという言葉が聞かれる。戦争の体験を語る人が少なくなるにつれて、その声は強まっている。それを聞くたびに思う。戦争体験者の声を聴くという行為が、却って彼ら、彼女らを苦しめ、傷つけることにならないか。それにより、真実を語らなくなることにつながらないか。
私が両親と暮らしたのは高校を卒業するまでの18年間であったが、不思議なことにあまり戦争について多く語り合った思い出がない。話題に出ないわけではなかったが、いつも決まっていた。父が大陸での戦闘で片方の耳が聞こえなくなったこと、母が東京大空襲で大変な思いをして逃げ回ったこと、親戚が中国から引き揚げてくる途中で幼子を死なせてしまったこと、友人が原爆投下後に長崎に親族を探しに行って、服の切れ端だけしか見つけられなかったこと。それ以外の話題は出なかったし、私もあえて聞かなかった。でも、子供ながらに、実際はその何百倍も残酷だったと想像することはできた。そして、言いたくないことは聞いてはならないと強く感じ取った。
父は10年前に97歳で亡くなった。101歳の母は認知症で私のことも分からない状態である。8月に戦争の話題が出ると、両親はもうそれに心乱されることはないのだ、とほっとしている自分がいる。本当の体験は、つらければつらいほど語ることができないのではないか。いや、むしろ忘れようとするのではないか。それを聞き出そうとすることは、却ってその人を苦しめることになるのではないか。では、どうしたら戦争の事実を後世に伝えていくことができるだろうか。
事実を伝えるのに重要なものが2種類あると考える。一つは、記録、すなわちデータである。人の記憶に頼るのではなく、記録やデータを分析していく必要がある。新たなデータを掘り起していく努力を続けるとともに、AIを含めたデータ分析の技術を使って、それらの関連性を明確にしていく。ここにこそ先端技術が役立つのではないか。眠っている資料を見つけ出し、冷静に読み込み、分析していく努力により、体験者の生の声を聴くのと同等の、あるいはそれ以上の「事実の解明」ができるような気がする。
もう一つは、人の心に訴えることである。そこには人間の感性、想像力、共感力が必要である。体験者の生の声を聴くことは、いずれできなくなる。バトンを受け取るべきは、戦争を体験していない、しかし、感じ取ることはできた我々の世代がかもしれない。しかし、それを感じ取ることのできた人もいなくなる。その先はどうすればよいのだろうか。
月並みな結論になってしまうかもしれないが、やはり先端技術を使う必要があるのではないか。思いつくのはメタバースである。データに基づいた戦争の真実を体験できる場を仮想空間に作る。戦争の残酷さ愚かしさを、仮想体験から人の感性に訴える。人間の想像力がまだ豊かで、人間がAIの奴隷にならないうちに、それを実現できないものだろうか。
自分の信念に従って行動する「高い志を持つ、市場価値の高い技術者」を育成します。
「市場価値の高い技術者の育成」を目指して、
コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

トップページ > コラム
戦争体験者の声をあえて聴かないこと
2025.9.7