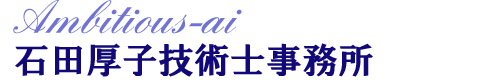最近、多言語学習のコミュニティのイベントで、複数言語を使ってシリコンバレー訪問の報告を行った。使ったのは、トルコ語、インドネシア語、ポルトガル語、英語である。2か月前から準備をした。話したい内容と流れは早くから決まっていたが、それを表現する言葉を見つけるのは非常に困難だった。英語を除けばどの言語もあいさつ程度しかできなかったからだ。それでも4つを組み合わせることによりできてしまった。3分間でプレゼンするというルールなのに5分くらいかかってしまったが。伝えたいことが明確であれば、複数言語を使うことで補い合って何とか伝えられるものだ、と実感できた瞬間だった。
同じころあるニュースに出会った。オランダの17歳の若者がサッカーでけがをして膝の手術を行った。麻酔が覚めた時、彼は母国語のオランダ語が全く話すことができなかった。その代わり、英語での会話ができた。彼にとって英語は学校の授業で習っただけで日常的に使うことはなかったし、英語圏に行ったこともなかったという。18時間後、ようやくオランダ語が理解できるようになり、24時間後には見舞いに来た友人たちと会話も可能になった。私の勝手な想像だが、麻酔により言語を理解する脳内の神経ネットワークの一部が麻痺してしまったのを、英語を理解する部分で補ったのではないか。
複数の言語を使うマルチリンガルの人達は認知症を発症するのが遅い、という研究結果が出ているようだ。マルチリンガルの人は言語を処理する脳内の神経ネットワークが発達していて、部分的にダメージを受けても他の部位が補って考えたりしゃべったりができることが関係しているのではないか。複数の言語を使うことで脳の機能のスイッチ切り替えが頻繁に起こり、脳の働きを高めることも理由であるらしい。
人間の脳と同様に、世界も多様なものが補い合って成り立っているはずだ。情報ネットワークの発達していなかった時代であれば、情報の共有は難しく、力と金を持つ強国のみが情報、技術、人材を抱え込み、拡大させることができた。しかし、情報が広く伝わる現代においては、一人の力よりもネットワークでつながった多数の力の方が強力に決まっている。それに加えて、多様性のあるネットワークからは、思いもかけないアイディアが創造できる可能性もある。ネットワークは補うだけでなく生み出す力も持っている。
昨年(2024年)秋にシリコンバレーを訪れた際に、サンノゼ市の方が示してくれたデータが衝撃だった。シリコンバレーでは60%がマルチリンガルだという。この値は米国内でも突出している。人種も、アジア系、ヒスパニック、白人が同じくらいの割合である。このような多様性がシリコンバレーで先端技術を生み出し、イノベーションを起こしたのは明らかである。
多様性のない社会の力には限界がある。人間は様々な力を持つ人や社会と協力しあって、補い合って問題を解決し、新しいものを生み出してきたのだ。もしも自国主義によってそれが後退していくとしたら、地球全体の将来に大きな損失が生じると思う。
私としてはこれからも多言語学習に励みたいと思っている。認知症予防のために。
自分の信念に従って行動する「高い志を持つ、市場価値の高い技術者」を育成します。
「市場価値の高い技術者の育成」を目指して、
コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

コンサルティングと研修のサービスを提供します。
所長:石田厚子 技術士(情報工学部門)博士(工学)

トップページ > コラム
補い合うことで実現できること
2025.4.6